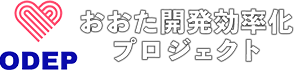先日、話題にあげた山形新幹線につづき、東海道新幹線においても走行装置にトラブルが発生しました。
多くのメディアに取り上げられており、ここでは詳細を割愛したいと思いますが、
ここで着目すべきは、運行再開の時期に両者で大きな違いが見受けられました。
山形新幹線は6月中旬にトラブルを確認して以来、現在も臨時列車を運休するなど、列車運行に大きな影響が出ています。
一方、東海道新幹線は7月末にトラブルを確認しましたが、数日で通常の列車運行に回復しております。
なぜ、このように対応が違うのでしょうか?
最たる理由がトラブルの形態にあります。
装置・システムのトラブル(故障・異常)は大きく2つに分けられます。
1)ランダム・ハードウェア故障
2)システマチック故障
1)ランダム・ハードウェア故障は、経年劣化、気候変動などの不確定な起因する故障であり、原因を一意に特定することがほぼ不可能です。
安全・品質の担保の確認手段としては、耐久試験などによって行われます。
また、故障の可能性については、「単位時間に対して何度故障するか」という観点で評価されます。
2)システマティック故障は、前者とは異なり技術上もしくは業務プロセス上に存在する欠陥に起因する故障であり、原因の特定が可能です。
安全・品質の担保の確認手段は各種試験、シミュレーション、レビューなど多岐にわたります。
これまでのメディア等の情報によると、
山形新幹線のトラブルは2)システマティック故障に当たるものと推測されます。
電源装置内の半導体の変更によるものと推測され、明らかに部品変更による検証不足、すなわち人為的要因とほぼ断定できます。
そのため、技術面・プロセス面で一貫性・完全性がなかったか再検証が必要であり、この部分が解決しないと通常運行に戻すことができません。
一方、東海道新幹線のトラブルは1)ランダム・ハードウェア故障に当たると推測されます。
走行装置の2つの部品で故障が発生しましたが、いずれも技術・プロセス要因ではないとのことです。
また、新幹線の耐用年数は凡そ15年ですので、安全に関わる構成部品となると100年~10000年の耐用年数が要求されます。
今回、独立した2つの部品で同時に故障が発生しており、これは最低でも10000年に1回レベルの極めて発生し難い故障と分類されます。
これにより、東海道新幹線は早い段階で通常運行を再開できたのです。
なお、東海道新幹線を運行するJR東海について、技術的知見・プロセス上の知見の蓄積に伴い、再発防止するための対策が検討されているということです。
最後になりますが、本記事はそれぞれの新幹線を運行する会社の責任を追及したものではありません。
故障の形態により、対応(方法、期間、コストなど)が異なることをお伝えしたかったのです。
もちろん、故障や異常が発生しないことが最も良いのですが、ほぼほぼ不可能なので、
発生しても影響を最小限に抑えることに重きを置く、これが現実的手段になります。